いくつかの発達理論は、社会で起こる変化のプロセスを理解しようとしています。 各開発理論は、独自の変化プロセスを提示し、さまざまな社会科学のアプローチと分野を利用しています。
依存関係理論と近代化理論は、それらを差別化する際立った考え方を持つ XNUMX つの有名なアプローチです。
主要な取り組み
- 従属理論は、後進国が資源と労働のために搾取する先進国に依存しているため、貧しいままであると仮定しています。 対照的に、近代化理論は、工業化、都市化、および文化的変化を通じて国が発展を達成できると主張しています。
- 依存関係理論は、開発の障壁としてグローバル経済システムと権力のダイナミクスに焦点を当てていますが、近代化理論は内部要因と西洋の進歩モデルの採用を強調しています。
- どちらの理論も、先進国と低開発国の間の格差を説明しようとしていますが、世界的な不平等の原因と潜在的な解決策について異なる視点を提供しています.
依存性理論と近代化理論
依存関係理論は、世界経済システムが裕福な国が貧しい国を犠牲にして発展することを可能にし、それが不平等につながることを示唆しています。 近代化理論では、すべての社会は同様の発展段階を経て進歩しており、したがって今日の低開発地域は過去のある時点での今日の先進地域と同様の状況にあると仮定します。
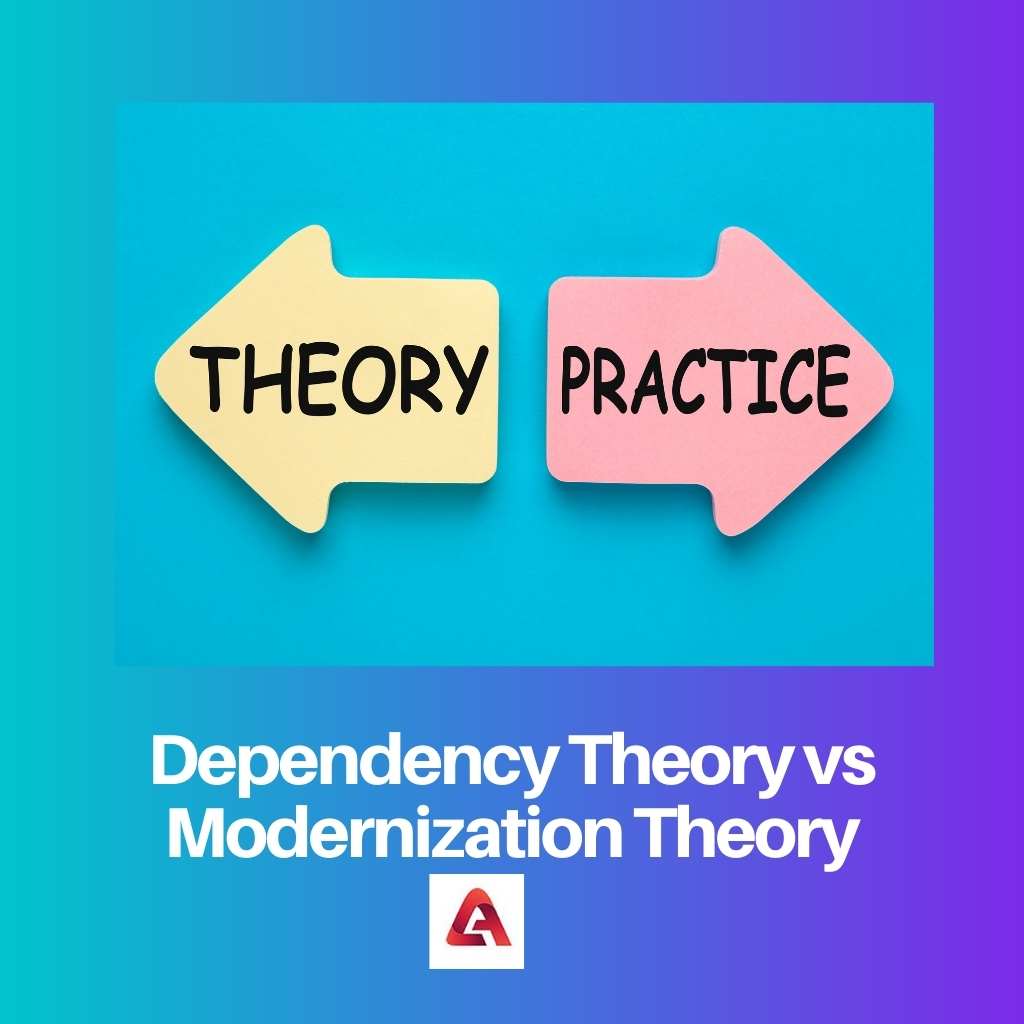
依存性理論とは、世界原理を理解しようとする研究を指します。 この考えによれば、裕福な国は、経済と他の要因との関係のために貧しい国を搾取することによって、富を増大させます。
1950年代後半、アルゼンチンの政治家と エコノミスト Raul Prebisch は依存性理論を提唱しました。 この理論は 60 年代と 70 年代に人気を博しました。
近代化理論は、社会の発展過程と社会進化を理解しようとしました。
古典的な近代化理論には主に XNUMX つの分析レベルがあります。それは、各国とその政治、社会、経済の近代化の明白なプロセスと経験的な軌跡に焦点を当てた近代化のマクロ経済的進化です。
もうXNUMXつは、近代化のミクロ経済的進化であり、社会的近代化の構成要素を強調しています。
比較表
| 比較のパラメータ | 従属理論 | 近代化論 |
|---|---|---|
| Origin | テクノロジーを強化することで、すべての国が裕福になり、貧しい国は近代化されたより豊かな国の道をたどる必要があります。 | ドイツの社会学者マックス・ウェーバー(1864年~1920年)の思想。 |
| 核心概念 | より豊かな国は、すべての貧困問題に解決策をもたらします。 | 近代化論を批判するために展開された。 |
| 主な焦点 | 発展途上国または貧しい国。 | 先進国と豊かな国。 |
| タイムライン | 50年代後半に開発されました。 | 先進国はそれを支持しています。 |
| 豊かな国 | 豊かな国は、世界的な貧困を生み出していると非難されています。 | それらは第三世界の国々によってサポートされています。 |
| サポート | 先進国はそれを支持しています。 | 先進国の支持を得ています。 |
依存性理論とは何ですか?
依存理論の基礎は、1950 年代にアルゼンチンの政治家で経済学者のラウル・プレビッシュによって明らかになりました。
この理論は、発展した第一世界の国ではなく、第三世界の国に由来するという点で、他の開発理論とは異なります。
第三世界諸国の依存思想家は、自国が置かれている不当で不平等な状況に懸念を抱いていました。 彼らの主な焦点は、不平等の理由を見つけることでした。
この理論の主な命題は、
- 第三世界の国々は孤立して存在しません。 第三世界諸国の政治的出来事は、第一世界諸国の政治問題に関連しています。
- 先進国の経済的および政治的出来事は、第三世界の経済と政治に大きな影響を与えます。 それでも、第三世界諸国の経済的および政治的出来事は、第一世界諸国の経済と政治に影響を与えます。
- 経済と政治は相関しており、経済貿易は先進国と発展途上国の間のギャップを縮小するどころか拡大します。
- 先進国は、第三世界諸国の低開発の理由です。
- 限り 資本主義 世界の政治経済にとどまらず、先進国と途上国の状況は変わらない。
依存理論の思想家は、彼らの主な関心事である「不平等」を解決するためのアドバイスも提供しました。 彼らは、共通の取引ブロック、市場、またはカルテルを形成することを提案しました。
コアの共通戦線を形成することにより、第三世界の国々が活用されます。 彼らはまた、第三世界の国々のエリートが自国の依存状態に立ち向かう責任を負うことを示唆した.
エリートは、豪華な製造業ではなく、国の文学プログラムや建設プロジェクトに投資するよう提案されました。
近代化理論とは?
第二次世界大戦の終わりまでに、ラテンアメリカ、アジア、およびアフリカの多くの国が危険にさらされました。 資本主義、しかし、彼らは開発に失敗し、貧しいままでした。 この文脈で、近代化理論は 40 世紀の 20 年代後半に展開されました。
この理論は、第三世界の国々に非共産主義の貧困解決策を与えることを目的としていました。 その主な目的は、民主的な西洋の価値観を促進することによって、特に資本主義的で工業化された開発モデルを開発することでした。
この理論には XNUMX つの主要な側面があります。それは、第三世界の国々における低開発の背後にある理由を説明し、解決策を提案することです。
現代化された思想家によると、第三世界の国々は発展途上にあり、発展途上にあるというのは、先進国の道をたどることを妨げているいくつかの文化的障壁があるためです。
彼らは、第三世界の国々は先進国の道をたどり、文化的価値を取り入れ、工業化を通じて経済を出現させる必要があると示唆しました。
そのためには、西側先進国からの投資と援助による支援が必要です。
この理論は、産業資本主義の開発モデルを支持しています。 近代化された思想家は、資本主義は工場ベースの生産システムを開発するプロセスである工業化を通じて効率的な生産を促進すると信じていました。
依存性理論と近代化理論の主な違い
- 依存性理論は、1950 年代後半にアルゼンチンの政治家で経済学者のラウル・プレビッシュによって最初に提唱されました。 一方、近代化論の起源は、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーの思想です。
- 依存理論によれば、一部の国は、特に植民地化を通じて、他の弱い国を搾取することによって豊かになりました。 一方、近代化理論は、技術を向上させることによってすべての国が豊かになり、貧しい国は近代化されたより豊かな国の道をたどる必要があると述べています。
- 依存理論の主な焦点は、開発が遅れている貧しい国です。 それどころか、近代化理論の主な焦点は、先進国と豊かな国です。
- 依存性理論は、1940 年代に開発された近代化理論よりも後に開発されました。 依存性理論は、近代化理論の作用として展開されました。
- 従属理論は世界の貧困の原因を先進国のせいにしているのに対し、近代化された理論は第三世界の発展途上国の貧困のせいにしている.
- https://www.proquest.com/openview/4039da2e926a00f581534e12d7421167/1?pq-origsite=gscholar&cbl=47510
- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220387108421356
最終更新日 : 25 年 2023 月 XNUMX 日

Piyush Yadav は、過去 25 年間、地元のコミュニティで物理学者として働いてきました。 彼は、読者が科学をより身近なものにすることに情熱を傾ける物理学者です。 自然科学の学士号と環境科学の大学院卒業証書を取得しています。 彼の詳細については、彼のウェブサイトで読むことができます バイオページ.
